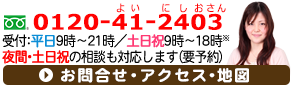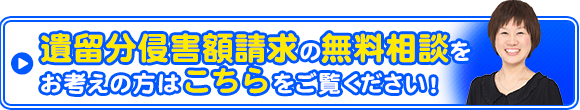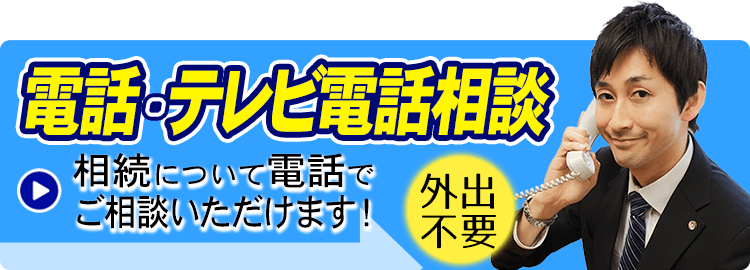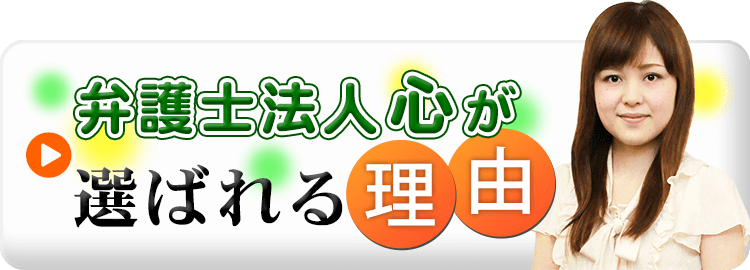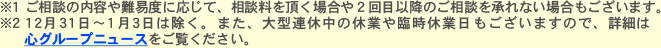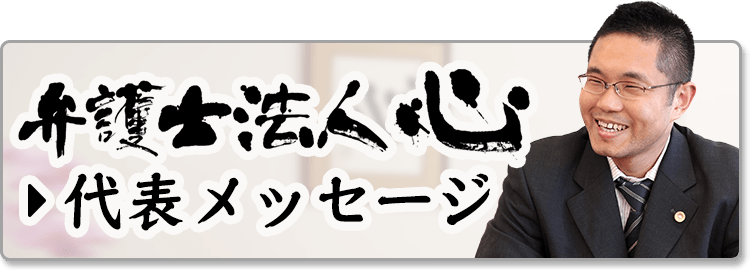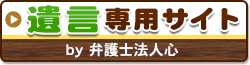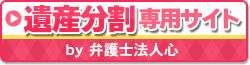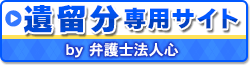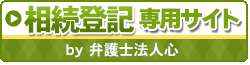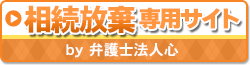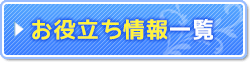生前贈与についても遺留分を請求できますか?
1 生前贈与についても遺留分を請求できる場合がある
生前贈与についても、遺留分を請求することができる場合があります。
民法は、遺留分を算定するための財産の価額として、被相続人が相続開始の時において有する価額に、その贈与した財産の価額を加えた額から、債務の全額を控除した額とする旨規定しています。
2 算入する生前贈与の範囲
もっとも、民法は、どのような生前贈与であっても、遺留分を算定するための財産の価額として算入できるとはしておらず、一定の制限を設けています。
まず、民法は、相続人以外の第三者に対する生前贈与については、相続開始前の1年間にされた贈与に限り、遺留分を算定するための財産の価額として算入できる旨規定しています。
つまり、相続人以外の第三者に対する生前贈与については、相続開始の1年前までにされた贈与に限り、遺留分を請求することができます。
ただし、民法は、生前贈与の当事者双方が、遺留分の権利者に損害を加えることを知ってした贈与について、相続開始の1年前よりも過去にされたものであっても、遺留分を算定するための財産の価額として算入できる旨規定しています。
ですので、その場合は、相続開始の1年前よりも過去の生前贈与であっても、遺留分を請求することができます。
また、民法は、相続人の1人に対してなされた生前贈与については、それが、「婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与」に該当し、かつ、相続開始前の10年間になされた贈与であれば、特別受益と評価される価額に限り、遺留分を算定するための財産の価額として算入できる旨規定しています。
つまり、相続人に対する生前贈与については、相続開始の10年前までになされた、「婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与」であれば、遺留分を請求することができることになります。
兄弟に遺留分は認められるのかについてのQ&A Q&Aトップへ戻る