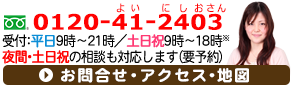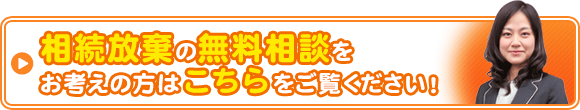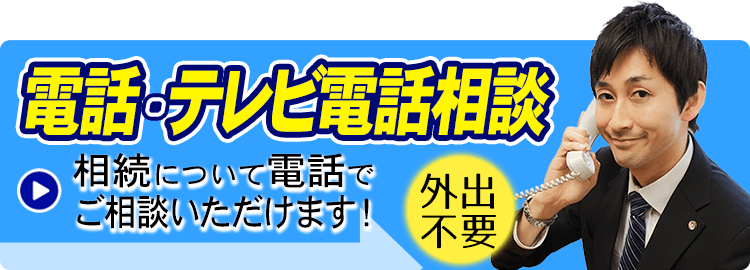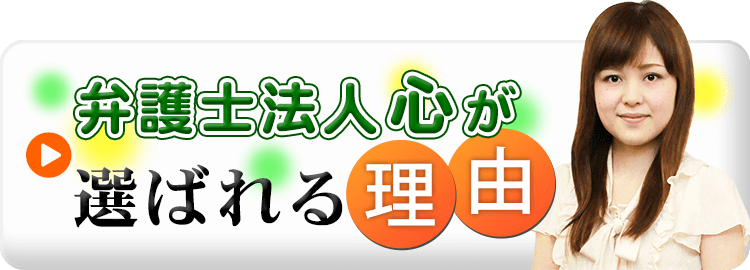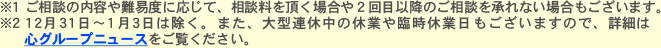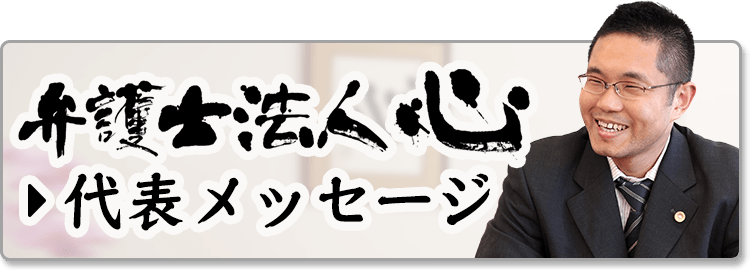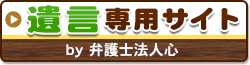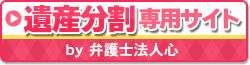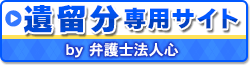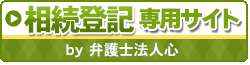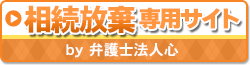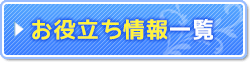相続放棄の理由と申述書の書き方
1 相続放棄の申述書と理由
相続人自身で相続放棄を申し立てる場合、家庭裁判所に相続放棄することを申し立てる書類である申述書も、相続人自身で作成することになります。
その場合、申述書の書式として、裁判所が定めたものが用いられることがあります。
申述書の書き方は、裁判所の書式を参照してください。
申述書には申述人と被相続人、申述の趣旨として相続の放棄をすること、そして、申述の理由として、相続のあったことを知った日や、相続放棄の理由、相続財産と負債について記載することになります。
2 相続放棄の理由
相続放棄の理由は、相続放棄の要件に該当しません、
ですので、相続放棄する理由は、どのようなものでもかまいません。
裁判所の書式では、相続放棄の理由として
- 〇 被相続人から生前に贈与を受けていること
- 〇 生活が安定していること
- 〇 遺産が少ないこと
- 〇 遺産を分散させたくないこと
- 〇 債務超過していること
及びその他の事情から選択することができるようになっています。
もっとも、相続放棄する理由に制約はありませんので、その他の事情を選択して、自由に記載してもらってもかまいません。
3 その他、相続放棄の理由になる場合
相続放棄の理由になる場合として、さまざまな事情が考えられます。
例えば、先ほど挙げた債務超過している場合のほか、被相続人が連帯保証人になっている場合も、債務超過している場合と同じように考えることができます。
また、債務超過しておらず、遺産がある場合であっても、管理したくない財産がある場合、つまり、先祖代々引き継いだ山、沼や荒れ地などの、どこにあるか分からない、引き継いでも管理しきれないような財産がある場合も、相続放棄する理由になり得るでしょう。
さらに、財産や債務と関係がない場合でも、相続人が多数いる場合、付き合いのない親戚と会ったり、相続争いに巻き込まれたりすることがあって煩わしいと考えるような場合だと、相続放棄する理由になり得るでしょう。