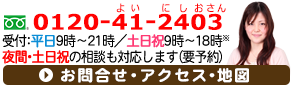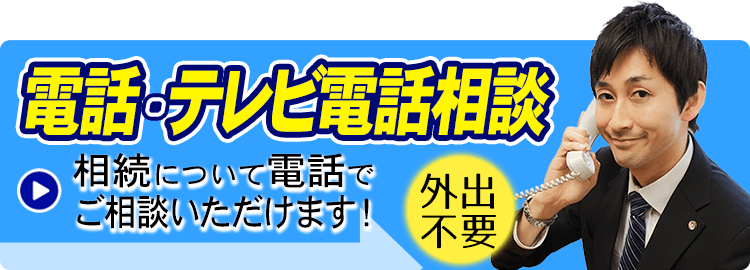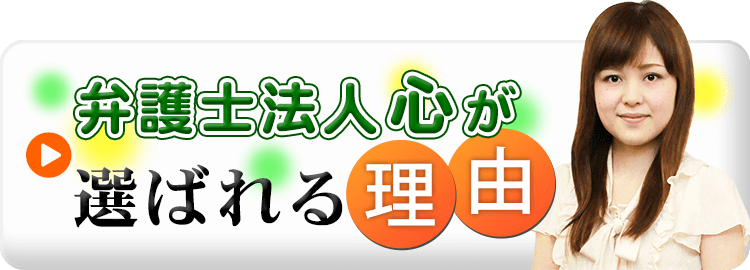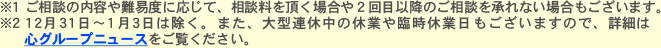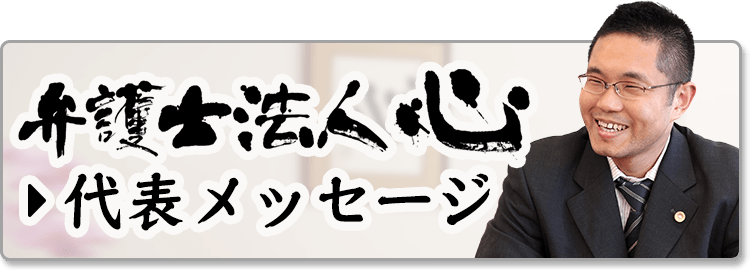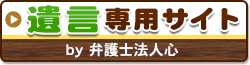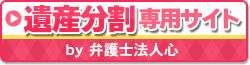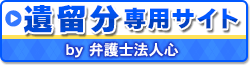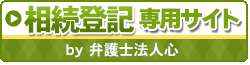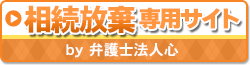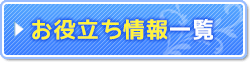遺産分割の流れ
1 遺産分割手続きは3段階に分かれる
遺産分割の手続きの全体像としては、大きく遺産分割協議の段階、遺産分割調停の段階、遺産分割審判の段階に分かれます。
遺産分割協議は、お互いに交渉を行い、遺産の分け方を話し合う段階で、調停は第三者を交えた話し合いを行う段階、審判は裁判所によって後見的に遺産の分割が行われる段階です。
遺産分割協議の段階はさらに、遺言書の有無を確認し、相続人や被相続人の戸籍から相続人を確定し、遺産分割協議を行うという流れがあります。
以下詳述します。
2 遺産分割協議の流れ
⑴ 初めに遺言書の有無を確認する
遺言書がある場合、遺言書に従って遺産を分割することができるため、まずは遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書が保管されていると考えられる場所としては、被相続人の自宅や、公証役場、法務局等の場所が考えられます。
公証役場に遺言が保管されているかの確認については、全国の公証役場で遺言検索システムを使用することで探すことができます。
費用は無料ですが、必要書類が複数個ありますので詳しくは下記のサイトをご参照ください。
参考リンク:日本公証人連合会「亡くなった方について、公正証書遺言が作成されているかどうかを調べることができますか?」
法務局に遺言書が保管されているかの確認については、全国の法務局で、遺言書保管事実証明書の交付を請求することで確認することができます。
こちらは、証明書の費用は1通800円で、複数の必要書類が要求されています。詳しくは下記のサイトをご参照ください。
参考リンク:法務省・自筆証書遺言保管制度
⑵ 相続人の確定
遺言書が無いことを確認した後には、戸籍の収集を行って他の相続人の有無を確認する必要があります。
具体的に相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を収集し、子や親、兄弟姉妹等の相続人になりうる方々が生存しているかを確認する必要があります。
戸籍の集め方に関しては、令和6年3月1日より広域交付の制度が開始するため、直系の親族の戸籍が最寄りの市区町村役場で取得できるようになります。
詳しくは、下記のサイトをご参照ください。
参考リンク:法務省・戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
集めた戸籍の読み方が分からない場合には、お気軽にお電話ください。
⑶ 遺産分割協議書の作成
相続人の確定ができた後には、相続人との連絡を実際にとって遺産分割協議書の作成について話し合うことになります。
被相続人の遺産(考えられる遺産の例は下記表参照)を把握して、相続人間で誰がどの遺産を取得するかを話し合います。
遺産の分割方法で合意ができた場合には、遺産分割協議書を作成して、合意内容通りの文書を打ち込み、相続人全員の実印による押印と印鑑証明書を取得しましょう。
遺産の分割方法で合意ができなかった場合には、遺産分割調停の申し立てを行って次の手続きに移行することになります。
* よくある遺産の種類
| 土地・建物 |
| 事業用財産(商品、減価償却資産) |
| 現金・預貯金 |
| 有価証券等(株式、投資信託、NISA口座等) |
| 家庭用財産(車、電化製品、ブランド品等) |
| その他の給付金・還付金等(家賃、入院給付金、還付された税金等) |
3 遺産分割調停
遺産分割協議が整わなかった場合には、家庭裁判所に対して遺産分割調停の申し立てを行う事になります。
遺産分割調停では、調停委員が相続人それぞれの話を聞き、第三者の立場から相続人同士で折り合いがつけられそうな妥協点を提案してくれることになります。
⑴ 必要書類
申し立てを行う際には以下の書類を家庭裁判所に提出する必要があります。
<申請書関係>
| 当事者目録 |
| 財産目録 |
| 相続関係図 |
| (特別受益目録) *主張する場合のみ |
<身分関係>
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍(*1) |
| 相続人全員の現在戸籍(3か月以内の原本) |
| 被相続人の住民票の除票(廃棄済みなら戸籍の附表) |
| 相続人全員の住民票(3か月以内の原本) |
*1 被相続人の地位によって違いがありますのでご注意ください。
<不動産関係>
遺産に不動産がある場合で、財産目録に記載して申し立てする場合には、追加で以下の書類が必要です。
| 登記事項証明書(3か月以内の原本) |
| 固定資産税評価証明書(3か月以内の原本) |
<不動産以外のその他の遺産>
遺産に不動産以外のその他の遺産がある場合で、財産目録に記載して申し立てする場合には、追加で以下の書類が必要となる場合があります。
| 預貯金の残高証明書の写し |
| 株式の残高証明書の写し |
| 公図写し |
| 自動車の登録事項証明書 |
| 相続税申告書 |
| 遺言書の写し |
⑵ 費用
被相続人1人につき、収入印紙1200円です。
それ以外にも、郵券複数枚を裁判所に納める必要があります。
必要書類・費用については、詳しくは裁判所のサイトリンクをご確認ください。
参考リンク:裁判所・遺産分割書式集
⑶ 弁護士に依頼する場合
弁護士に依頼することで、申し立てに必要な書類の収集代行や、調停期日の代理での出席をすることができます。
お客様のお仕事が忙しい場合や、相続人との交渉を全て任せたいと考えている場合には弁護士に依頼するメリットがあるといえます。
弁護士法人心では、遺産分割協議に関する案件として調停に関するご相談を初回無料で受け付けております。
また弁護士法人心では、原則着手金無料で調停事件をお受けすることができます。
詳しい費用はこちらのページをご参照ください。
4 遺産分割審判
遺産分割審判は、裁判官が後見的に遺産分割の方法を決める手続きを指します。
裁判官が、相続人各人の意見を聞いて、遺産分割の方法を法律や規範に従って決定する点で調停とは異なります。
遺産分割審判の前に遺産分割調停を申し立てない場合には、以下の書類が必要となります。
なお、調停を申し立てている場合には、調停不成立となった後に、そのまま審判に移行しますのでこれらの書類の追加提出は不要です。
⑴ 必要書類
<申請書関係>
| 当事者目録 |
| 財産目録 |
| 相続関係図 |
| 申し立ての実情を書いた書面 |
| (特別受益目録) *主張する場合のみ |
<身分関係>
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍(*1) |
| 相続人全員の現在戸籍(3か月以内の原本) |
| 被相続人の住民票の除票(廃棄済みなら戸籍の附表) |
| 相続人全員の住民票(3か月以内の原本) |
*1 被相続人の地位によって違いがありますのでご注意ください。
<不動産関係>
遺産に不動産がある場合で、財産目録に記載して申し立てする場合には、追加で以下の書類が必要です。
| 登記事項証明書(3か月以内の原本) |
| 固定資産税評価証明書(3か月以内の原本) |
<不動産以外のその他の遺産>
遺産に不動産以外のその他の遺産がある場合で、財産目録に記載して申し立てする場合には、追加で以下の書類が必要です。
これらの書類には、必ず「甲〇号証」等の表示が要求されるので忘れないようにしましょう。
| 預貯金の残高証明書の写し |
| 株式の残高証明書の写し |
| 公図写し |
| 自動車の登録事項証明書 |
| 相続税申告書 |
| 遺言書の写し |
⑵ 費用
被相続人1人につき、収入印紙1200円です。
それ以外にも、郵券複数枚を裁判所に納める必要があります。
⑶ 弁護士に依頼する場合
遺産分割審判は、裁判官が法律や規範にしたがって遺産分割の方法を決定します。
弁護士に依頼するメリットは、裁判官が納得しやすい法律上の主張を組み立ててくれる点にあります。
どんなに主張したいことがあっても、それが法律上どのような意義を持つのかを判断するのは非常に難しいことです。
審判手続きを行うのであれば弁護士に相談するのが良いといえるでしょう。
弁護士法人心では、原則着手金無料で審判事件をお受けすることができます。
初回相談料も無料ですので、こちらのページからお気軽にお問い合わせください。
自筆証書遺言のメリットやデメリット 相続放棄した方がよいケース