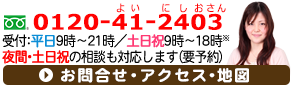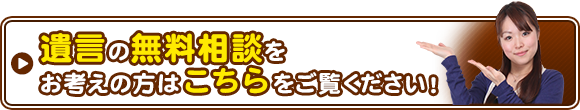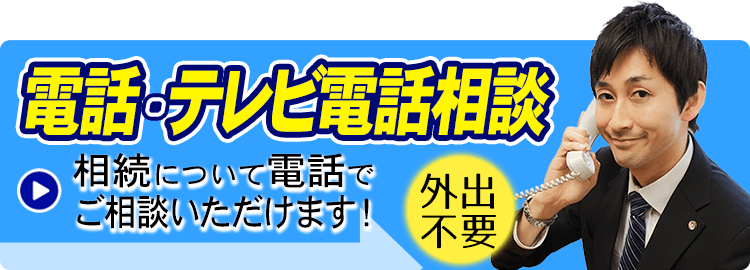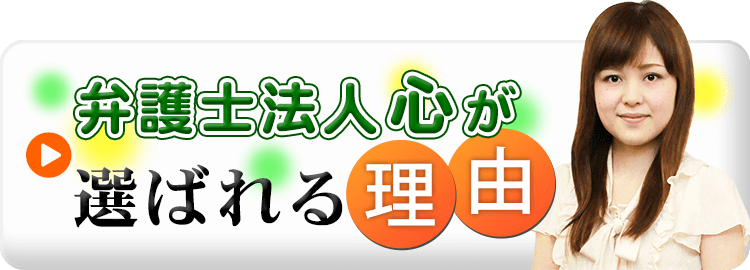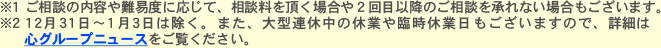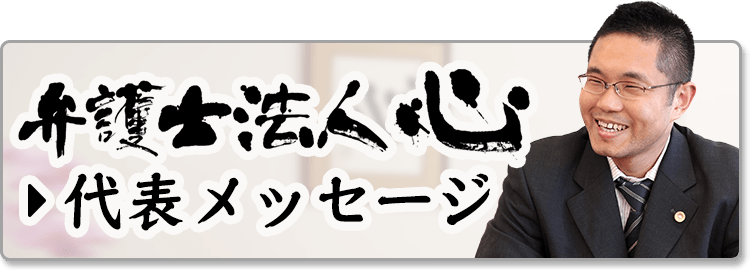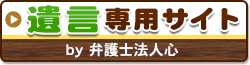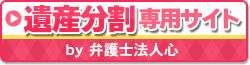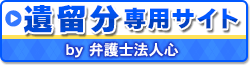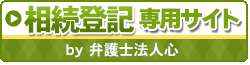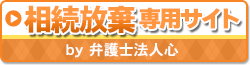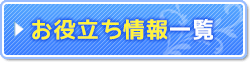自筆証書遺言のメリットやデメリット
1 自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が自筆で日付、氏名、遺言書の内容を書き、印を押すことによって作成する遺言です。
自筆証書遺言が有効に成立するためには、①遺言の内容となる全文(財産目録を除く)、②日付、③氏名の全てを遺言者が自筆し、④押印することが必要です。
2 自筆証書遺言のメリット
⑴ すぐに作ることができる
自筆証書遺言は、遺言者自身で作成するものですので、作成を決断してからすぐに着手することが可能です。
⑵ 費用がかからない
公正証書遺言を公証人に作成してもらう場合、公証人に支払う費用がかかりますが、自筆証書遺言の場合は、遺言者自身で作成しますので、費用はほとんどかかりません。
⑶ 遺言の存在を秘密にすることができる
自筆証書遺言は、遺言者自身で作成するものですので、誰にも内容を見られることなく作成でき、遺言の存在自体も秘密にすることができます。
3 自筆証書遺言のデメリット
⑴ 法律のルールが厳しく定められている
自筆証書遺言書の作成方法は、法律で厳しいルールが定められており、そのルールに反した場合は、遺言書の法的効力が認められなくなってしまいます。
⑵ 偽造又は変造の可能性がある
自筆証書遺言は、遺言者自身が自筆で作成できるため、遺言が発見されたとしても、その遺言が遺言者以外の誰かによって加筆や訂正がされて、偽造又は変造されたのではないかと疑われる可能性があります。
⑶ 未発見や紛失の可能性がある
自筆証書遺言は、遺言者自身が誰にも内容を見られることなく作成できてしまうため、相続発生後に誰にも遺言が発見されない可能性や、相続発生前に紛失して発見されなくなる可能性があります。
もっとも、この点については、自筆証書遺言を作成した後で法務局に預ける手続をとることで、一定程度防止することができます。
⑷ 相続発生後に検認の手続が必要になる
自筆証書遺言が発見された場合、発見者は家庭裁判所へ「検認」という手続の申立てを行う必要があります。
検認とは、裁判所による、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
なお、自筆証書遺言を作成した後で法務局に預ける手続をとることで、検認が不要になります。