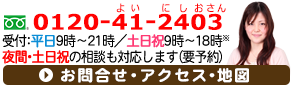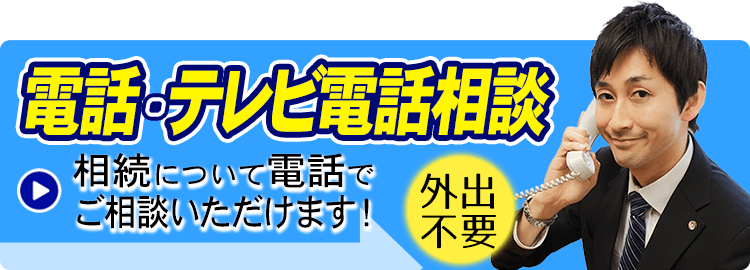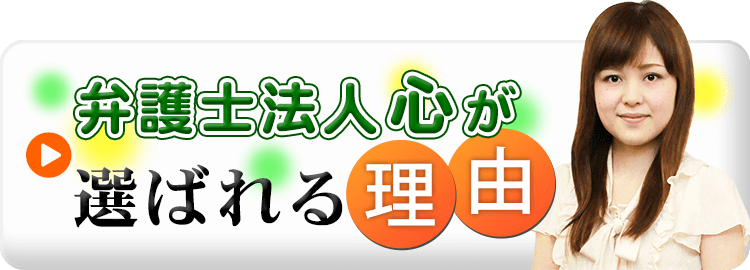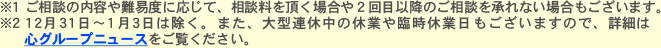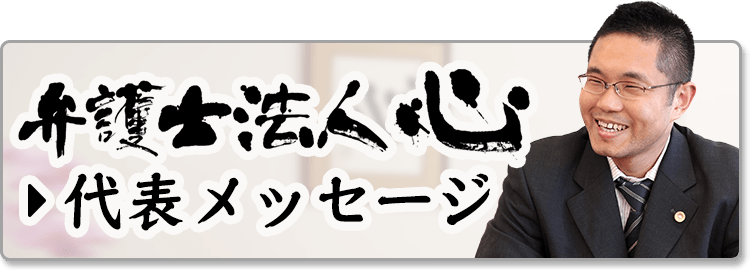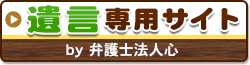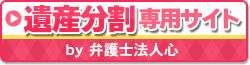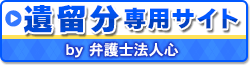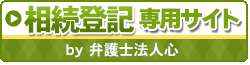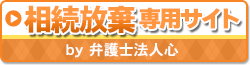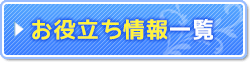特別寄与料と寄与分の違い
1 特別寄与料と寄与分の違い
相続が発生した際に、親の看護等を行なっていた場合、他の相続人に対して何らかの主張ができないでしょうかといったご相談は多いです。
その際、特別寄与料や寄与分といった制度によって主張をすることができますが、その制度の違いについて解説していきたいと思います。
特別寄与料と寄与分の違いは大きく分けて、以下の3点です。
- ①請求権を行使できる権利者
- ②請求権を行使できる要件
- ③時効
以下詳述します。
2 請求権を行使できる人
まず、寄与分とは、相続人が被相続人に対して、労働の提供、又は金銭の支出、療養看護等を行なっていた場合に、相続財産からそれらの対価を得る制度です。
次に、特別寄与料とは、相続人以外の第三者が被相続人に対して、療養看護を行なっていた場合、相続財産からその対価を得る制度となっています。
これらの定義から分かるとおり、寄与分は相続人が権利者となり、特別寄与料では相続人以外の第三者が権利者となります。
相続人以外の第三者とは、例えば妻や、内縁の妻、孫が想定されます。
そのため、寄与分と特別寄与料の違いの1点目は、請求権を行使できる主体が違うという点にあるといえます。
3 請求権の認められやすさ
⑴ 行使できる場合についての違い
次に、寄与分を請求する為の要件として、相続人が被相続人に対して、
- ①労働を提供していた場合(例:被相続人の会社で無償で働いていた場合等)
- ②金銭を支出していた場合(例:被相続人に代わって相続人の支出で被相続人の施設代を払っていた場合等)
- ③療養看護を提供していた場合(例:被相続人の身の回りの世話をしていた場合等)
のいずれかに該当しなければなりません。
これに対して、特別寄与料は、①労働を提供していた場合、③療養看護を提供していた場合についてのみ認められる権利です。
したがって、行使できる場合について、特別寄与料よりも寄与分の方が広い範囲で認められるといえます。
⑵ 認められやすさの違い
もっとも、寄与分は広い範囲で行使できるものの、裁判所が寄与分を認めるハードルはかなり高いです。
なぜなら、被相続人と相続人は相互に扶養義務(最低限の生活を保障しあう義務)を負っています。
そして、寄与分はこの扶養義務を超えた「特別な貢献」が認められる場合にのみ、認められる請求権となります。
例えば、被相続人が会社を行なっていた場合に、相続人が給料を貰わないで働いていた等の場合は、原則として「特別な貢献」があったといえます。
また、療養看護では、相続人が偶に被相続人の様子を見に行っていたという程度では足りず、つきっきりで介護を行い、ヘルパーや介護士による看護を必要としなかったといえる場合などに、原則として「特別な貢献」があったといえます。
これらのことから、寄与分が認められるには相当ハードルが高いといえます。
これに対して、特別寄与料では、第三者と被相続人の間に扶養義務がない場合が多く、寄与分と比較して緩やかに認められる場合があります。
とはいえ、特別寄与料であっても、ヘルパーや介護士による看護を必要としなかった事から、被相続人の財産からの支出を免れたといえる関係が必要となるため、認められるハードルはそれなりに高いといえます。
以上より、寄与分と特別寄与料には、認められやすさの点でも違いがあります。
4 時効
そして、特別寄与料と寄与分には時効の点でも違いがあります。
特別寄与料は、
- ①相続人及び相続の開始を知った時から6ヶ月以内
- ②相続の開始をから1年以内
これらの期間内に相続人に対して何らかの請求を行わなければ、特別寄与料は時効によって消滅してしまいます。
これに対して、寄与分は、相続開始から10年という制限があります。