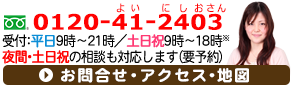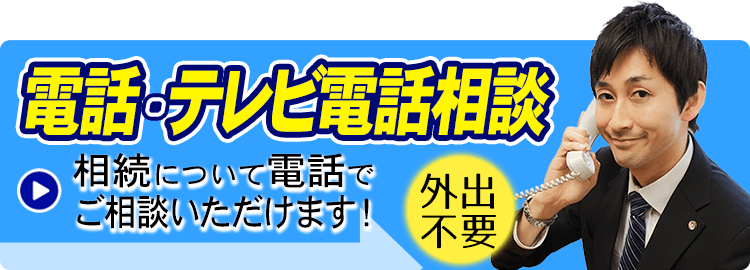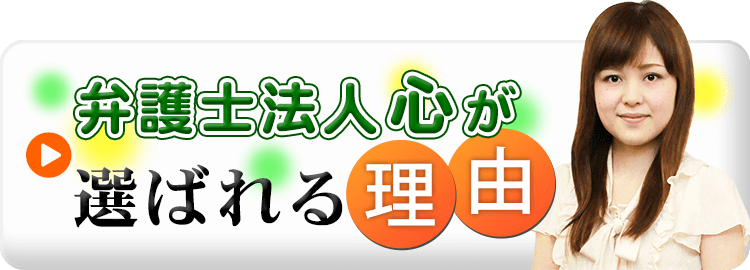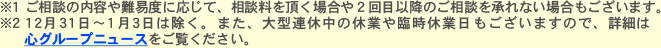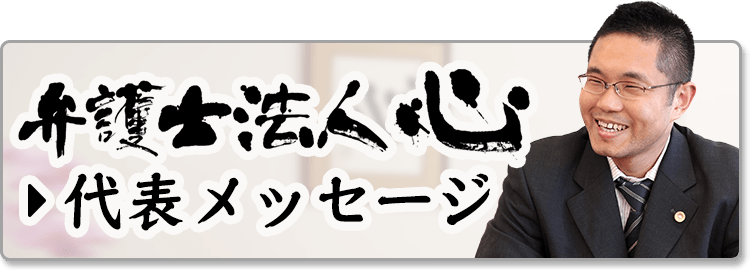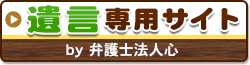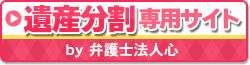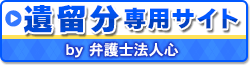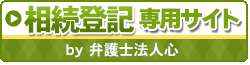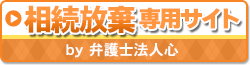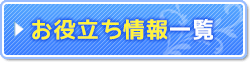代襲相続で起こりやすいトラブル
1 代襲相続について
代襲相続は、法定相続人となるはずだった者(推定相続人)が、相続開始前に死亡するなどの理由で相続人となることができない場合、その者の子がその者に代わって相続する制度を言います。
代襲相続は、推定相続人が被相続人の子であるときのその子、つまり被相続人の孫の場合と、推定相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合のその子、つまり被相続人の甥姪の場合に認められます。
代襲相続人は、推定相続人の相続分を引き継ぎます。
また、代襲相続人が複数人いるときは、その相続分をさらに分けることになります。
2 代襲相続で起こりやすいトラブル
代襲相続の際に起こりやすいトラブルとしては、以下のようなものが挙げられます。
⑴ 代襲相続人が無視される
他の共同相続人が、代襲相続人の意向を無視して遺産分割協議を進めようとする場合があります。
このようなことになるのは、そもそも代襲相続という制度があることを知らずに、孫や甥姪に代襲相続されることを把握していない場合があります。
また、制度を知っていても、代襲相続人として孫や甥姪の存在がいることに気づかない場合もあります。
さらに、代襲相続人として孫や甥姪がいることをわかっているのに、あえてその存在を無視し、他の共同相続人だけで遺産分割協議をしてしまう場合もあります。
⑵ 相続放棄の強要
他の共同相続人が代襲相続人に対し、遺産分割協議に参加させないために相続放棄を強要する場合があります。
その際、他の共同相続人から虚偽事実の説明を受けたり、脅迫されたりして相続放棄をする場合がありますが、そのような場合、詐欺や脅迫に基づく相続放棄として、取り消すことができます。
⑶ 遺産の全容を教えない
代襲相続人が、他の共同相続人から遺産の全容を教えてもらえないまま、言われるがままに遺産分割に同意してしまう場合もあります。
この場合、錯誤や詐欺に基づく遺産分割として、遺産分割への同意を取り消すことができます。
⑷ 遺産分割協議の紛糾
一方、代襲相続人が遺産分割協議に参加した場合、代襲相続人が頑なに法定相続分どおりの相続を主張し、他の共同相続人の寄与分や特別受益の主張を認めないことで、協議が紛糾する場合もあります。
寄与分や特別受益の主張を否認し、法定相続分どおりの分割を主張することは代襲相続人の自由ですが、他の共同相続人から事情を分かっていないなどと強く反発され、協議を紛糾させる原因になります。
このような場合、当事者間の協議で解決することは難しく、家庭裁判所の調停や審判を利用し、寄与分や特別受益の事実を裏付ける証拠によって判断することになるでしょう。
3 代襲相続の際はご相談を
代襲相続が起こると、相続関係がより複雑になることがあるため、以上のようなトラブルが起こりやすいといえます。
相続のトラブルでお悩みの場合には、弁護士にご相談ください。