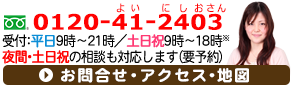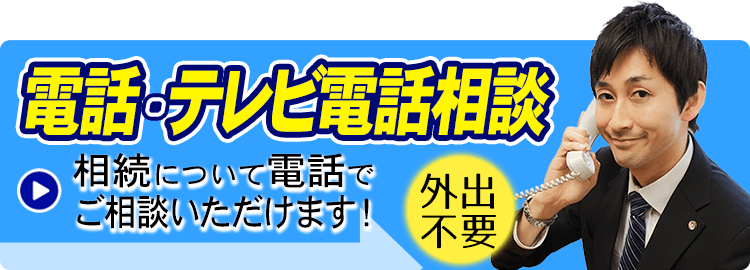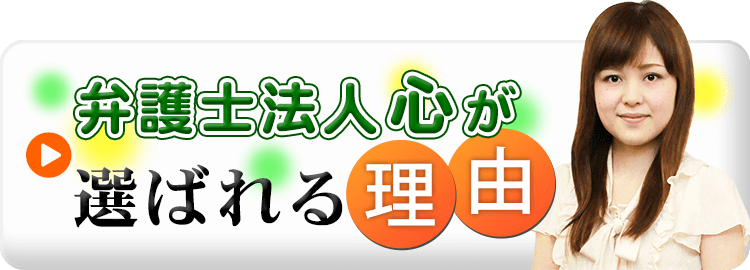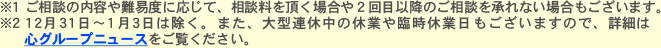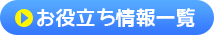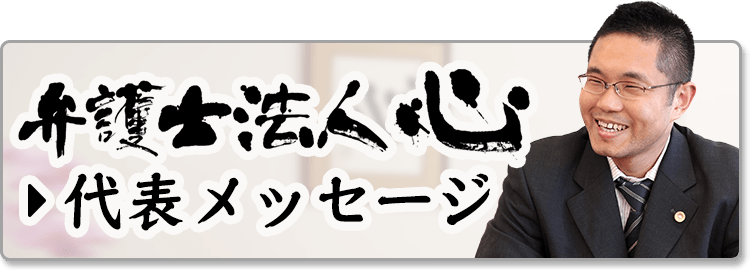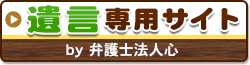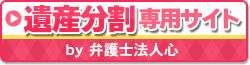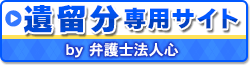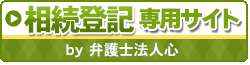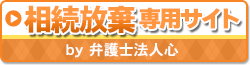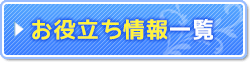相続財産調査
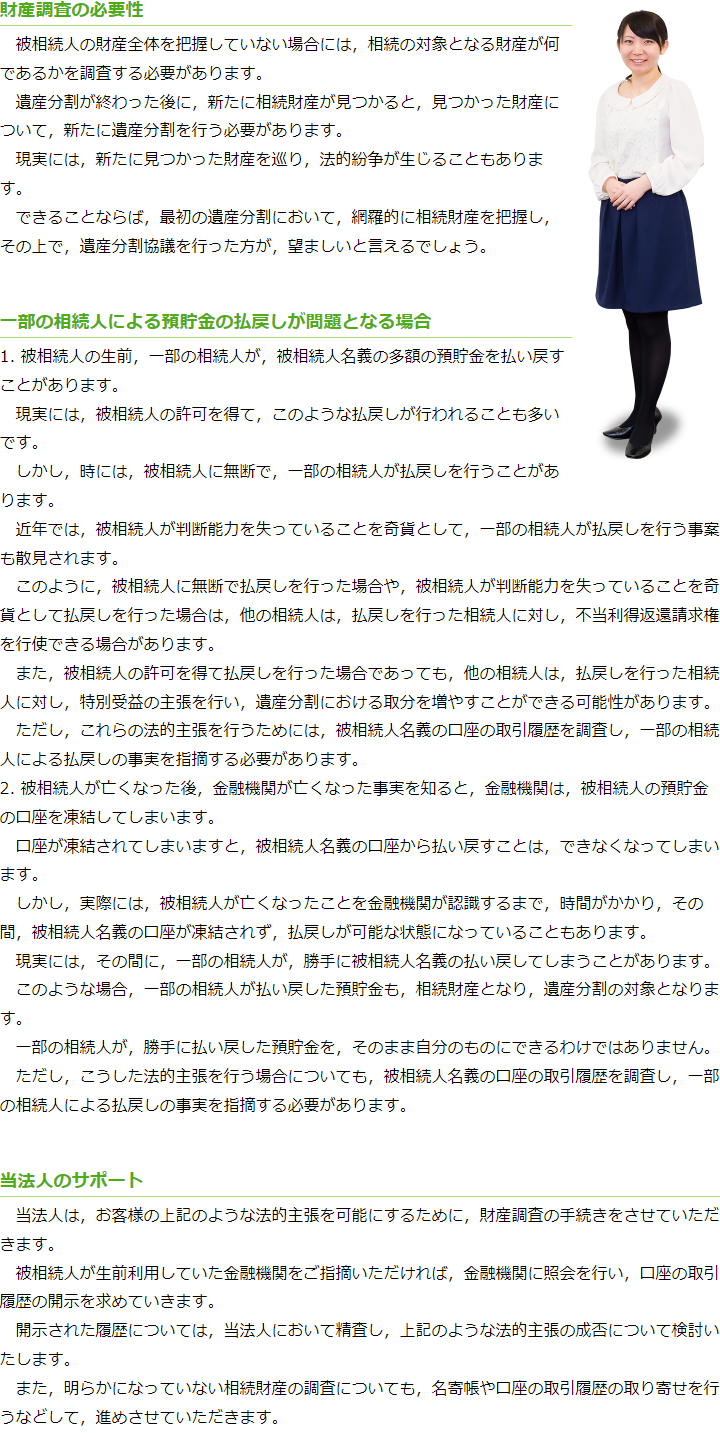
弁護士に依頼した場合の相続財産の調査方法
1 まずは相続人であることの証明作業を行います

相続財産は、ご家族が残した財産とはいえ、法律上は「他人の財産」ということになります。
そのため、まずは自己が相続人であるということの証明をして、財産の調査権限があることを示す必要があります。
相続人であることの証明は、戸籍謄本によって行います。
戸籍謄本は、市区町村役場などの窓口で取得することができます。
2 不動産の調査方法
誰が、どこの不動産を所有しているかという情報は、各市区町村が管理しています。
そのため、不動産の調査方法の第一歩は、各市区町村で名寄帳を取得することです。
名寄帳とは、その人が、その市区町村内で所有している不動産の一覧表です。
毎年、送られてくる固定資産税に関する通知にも、所有している不動産が記載されていますが、その不動産に共有者がいる場合、通知は共有者にだけ送付されている可能性があります。
不動産を漏れなく調査するためには、名寄帳を取得する必要性があります。
3 預貯金の調査方法
亡くなった方のご自宅にある、通帳やキャッシュカードをヒントに、取引があった金融機関の目星をつけます。
もし、一部の相続人が、通帳やキャッシュカードの情報を開示しない場合は、近隣の金融機関を手あたり次第、調査するなどして、預貯金の漏れがないようにしなければなりません。
各金融機関にそれぞれ問合せをしていく必要があります。
4 株式の調査方法
上場株であれば、証券保管振替機構に問い合わせることで、株式を所有していたかどうかが分かります。
非上場株式については、一元的に管理している機関がないため、亡くなった方の持ち物や通帳の履歴などから、非上場株がないかどうかを調べます。
5 債務の調査
もし、多額の債務があるような場合は、相続放棄も検討する必要があります。
そこで、相続財産の調査としては、債務の有無も確認しておく必要があります。
債務の調査は、信用情報機関と呼ばれる機関に問い合わせをすれば、ある程度把握することが可能です。
消費者金融や銀行などではなく、会社や個人への債務については、亡くなった方の職業、人間関係、通帳の履歴などから、推測していくことになります。