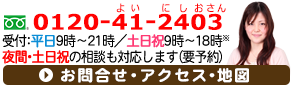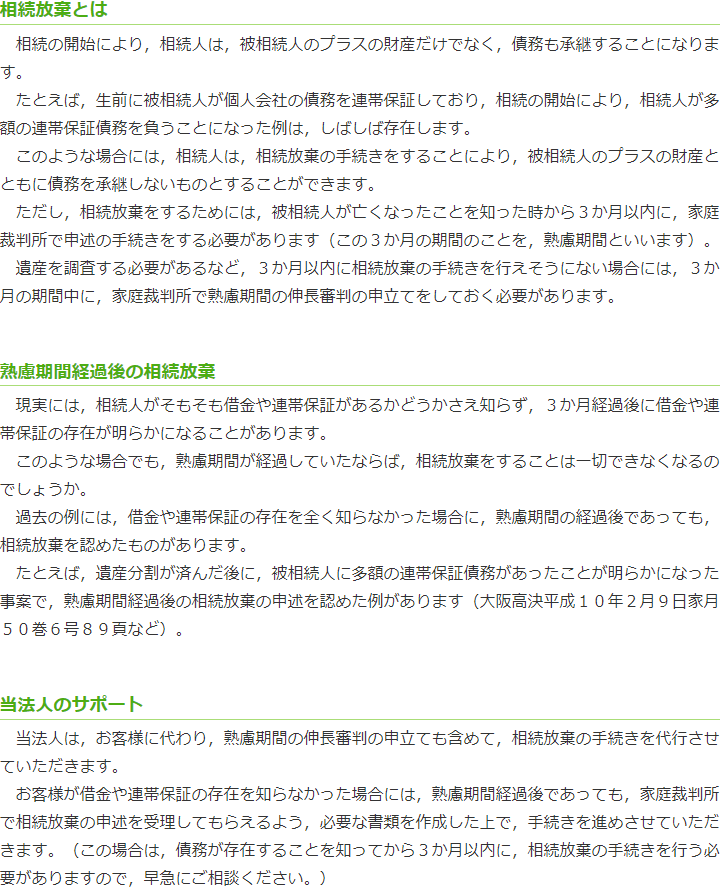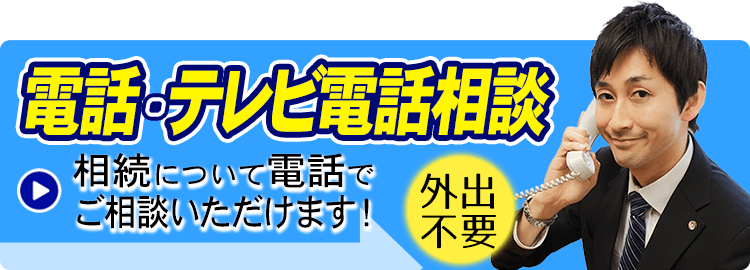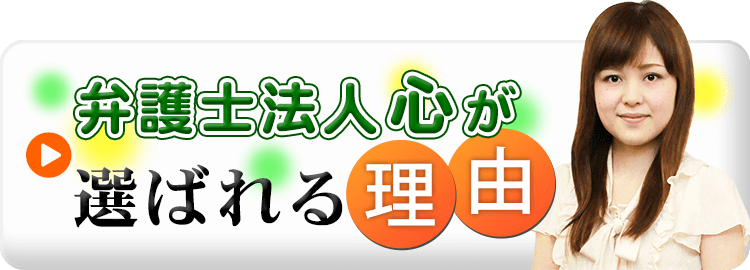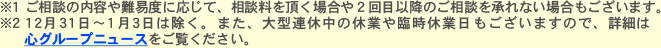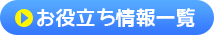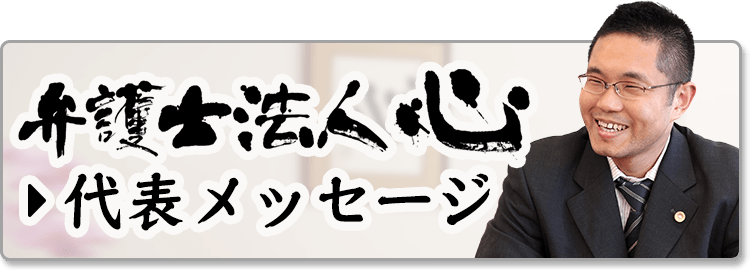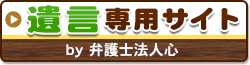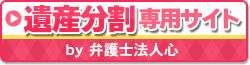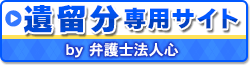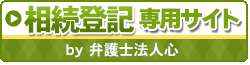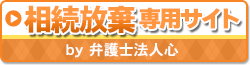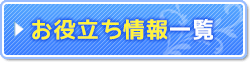相続放棄
事務所のご案内
当法人の事務所までの地図、お問合せ先などのアクセス情報はこちらからご覧いただくことができます。京都の事務所についてご案内しておりますので、ご確認ください。
相続放棄の期限
1 相続放棄の期限
民法は、相続放棄について、「自己のために相続の放棄があったことを知った時から3か月以内」に、相続放棄をしなければならないと規定しています。
その期間のことを「熟慮期間」と言います。
熟慮期間内に相続放棄をしなかった場合、相続人は、相続を単純承認したものとみなされ、相続放棄をすることができなくなります。
民法が相続放棄について熟慮期間を規定しているのは、仮に、期限を定めずにいつまでも相続放棄ができるとすれば、他の相続人や利害関係人の利益を害するなどの弊害があり、それを防ぐためです。
2 熟慮期間の延長
熟慮期間は、家庭裁判所に申立てをし、延長してもらうことができる場合があります。
たとえば、膨大な相続財産の調査に時間がかかるので、熟慮期間を経過してしまう可能性が高いような場合に、そのような申立てをすることが考えられます。
3 「自己のために相続の放棄があったことを知った時」の意味
熟慮期間の始まりである、「自己のために相続の開始があったことを知った時」は、単に被相続人が亡くなって相続が開始されたことを知っただけでは足りません。
「自己のために相続の開始を知った」と言えるためには、問題の相続について自分が相続人となったことを知ったことまでが必要です。
4 相続財産があることを知らなかった場合も相続放棄ができるのか
相続財産の中に借金があることを知らなかった場合、①被相続人が亡くなった事実も、②自分が被相続人の相続人であるという事実も知ってから3か月が経過したからといって、相続放棄ができなくなるのでしょうか。
この点、裁判所は、個別具体的な事情を考慮して、相続人が、先ほどの①②の事実を知ってから3か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産がまったく存在しないと信じたためであり、かつ、相続人においてそのように信じたことについて相当な理由があると認められるときは、相続人が「相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識すべき時」から熟慮期間が始まるとしています。
この場合、個別具体的事情を踏まえ、熟慮期間がいつから始まるのかについて、裁判所が厳密に判断することになります。
被相続人が亡くなってから3か月以内に相続放棄をしなかったけれど、被相続人に借金があるのが分かったので相続放棄をしたいと考えられている場合、相続放棄に詳しい弁護士に一度ご相談ください。