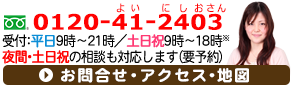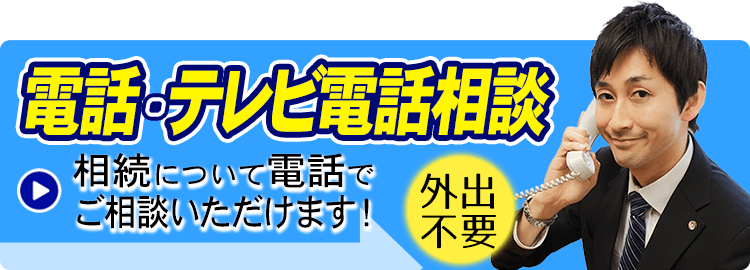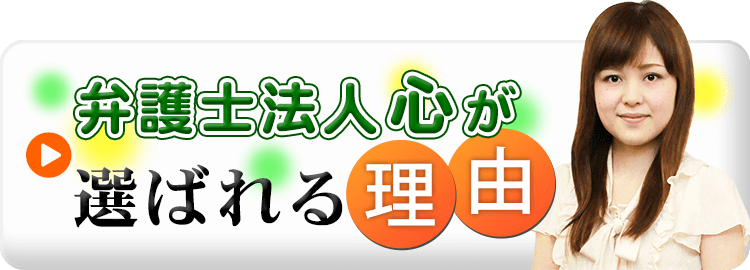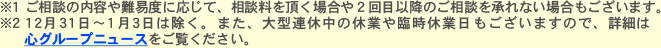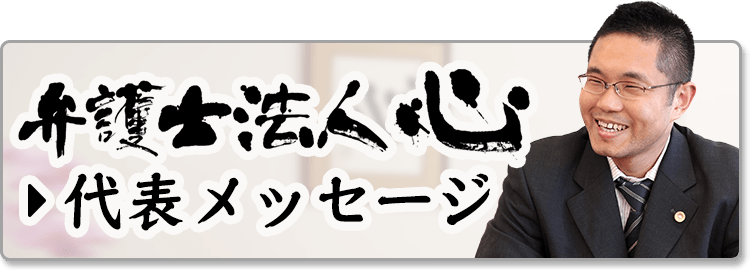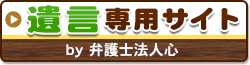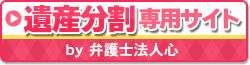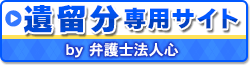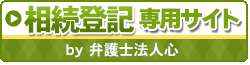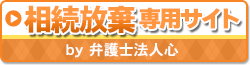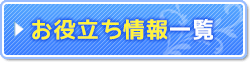相続登記は誰が申請するのか
1 相続登記の申請をする人
相続登記は、原則として不動産を取得した相続人が申請します。
相続登記は、相続が発生し、被相続人の相続財産に不動産が含まれているときに必要となります。
相続開始後、遺産分割協議や被相続人の遺言により、被相続人の不動産を取得することになった相続人が、相続登記の申請をすることになります。
その際、相続人が自ら相続登記の申請をする場合もありますが、多くは弁護士や司法書士といった専門家に相続登記を依頼し、自己の代理人として、代わりに行ってもらいます。
相続登記をする場合、誰がその不動産を取得するかが決まらなければ申請をすることができないのですが、それでは期限に間に合わないということがあります。
仮に、遺産分割協議がまとまる前に、法定相続分に従って相続登記をする場合、原則として相続人全員が相続登記の申請をしなければなりません。
なお、この場合、例外として相続人のうちの1人だけでも、法定相続人全員分の相続登記をすることはできますが、登記識別情報が発行されるのは申請した相続人の分だけになります。
2 相続登記を申請するまでの流れ
まず、相続人を確定する必要があります。
相続人の確定は、遺言や遺産分割協議によることになります。
遺言は被相続人が作成します。
一方、遺産分割協議は相続人全員が行うものであり、まとまれば、遺産分割協議書を作成することになります。
遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印で押印するとともに、印鑑証明書を添付します。
このようにして、不動産を取得することになった相続人は、相続登記を申請するための書類を作成したり、資料を収集したりすることになります。
相続登記の申請に必要となる書類は、相続登記申請書のほか、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人の戸籍謄本、遺言又は遺産分割協議書やそれに添付する印鑑証明書、被相続人の住民票・不動産を取得した相続人の住民票、固定資産評価証明書といった書類になります。
これらの書類をまとめ、登録免許税として定められた金額分の収入印紙を張り付け、管轄の法務局に提出して相続登記を申請することになります。
なお、相続登記を専門家に依頼した場合、書類の収集や作成、法務局への提出といった手続は専門家が代行してくれます。