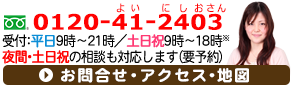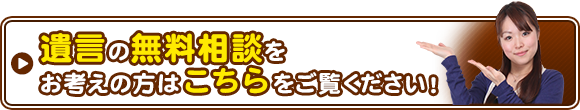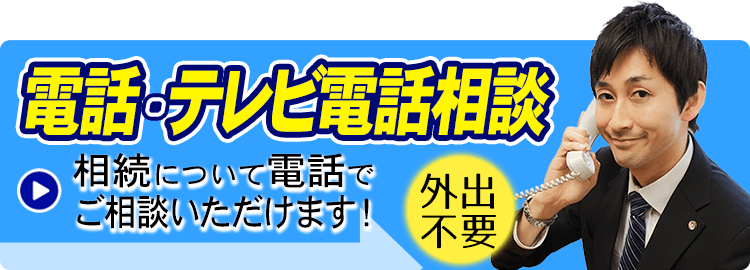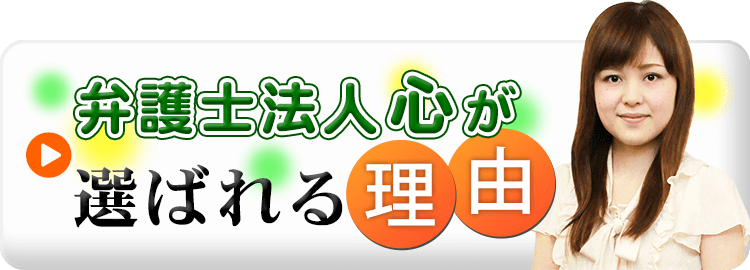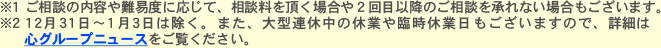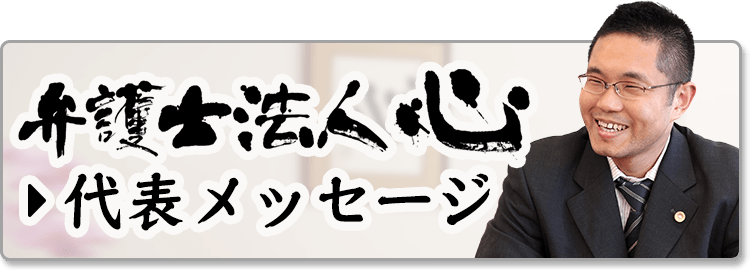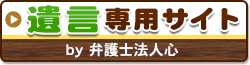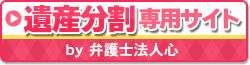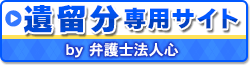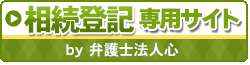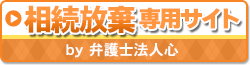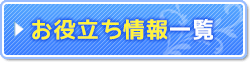認知症と遺言書についてのQ&A
認知症の診断をされると、遺言書の作成はできないと聞きましたが、本当ですか?
認知症の診断がされたとしても、遺言書の作成が可能な場合はあります。
認知症と一言で言っても、様々な段階があります。
最も重い状態になれば、自分の名前や、家族の名前も思い出すことはできなくなります。
そのような状態であれば、遺言書の作成は難しいでしょう。
他方、少し物忘れが出てきたり、最近の出来事について覚えおることができないといった程度であれば、遺言書の作成が可能な場合があります。
認知症の診断が出ていると、後で遺言書の無効の裁判を起こされないかが心配ですが、対処方法はありますか?
今のうちから、証拠を作成することが大切です。
通常、裁判になった場合は、過去の事実を証明するための証拠を集めることになります。
他方、将来的な裁判に備える場合は、今から証拠を作成することが可能であるため、このアドバンテージを最大限に生かす必要があります。
将来の裁判に備えて、どんな証拠を作成すればいいですか?
中立的な第三者で、かつ医師などの専門家が作成した証拠が必要です。
裁判になれば、医師などの専門家の判断が重視される傾向にあります。
かかりつけ医を証人として申請し、裁判で証言してもらう方法もありますが、多くの患者を抱えている意思が、患者一人一人の判断能力について覚えているかどうかは分かりません。
まして、遺言の作成からかなり年数が経ってしまっては、医師の証言の力が弱いと考えられてしまうかもしれません。
そこで、遺言作成時の判断能力について、医師の診断書を作成しておくことが大切です。