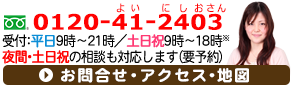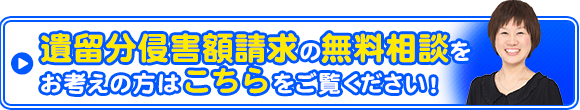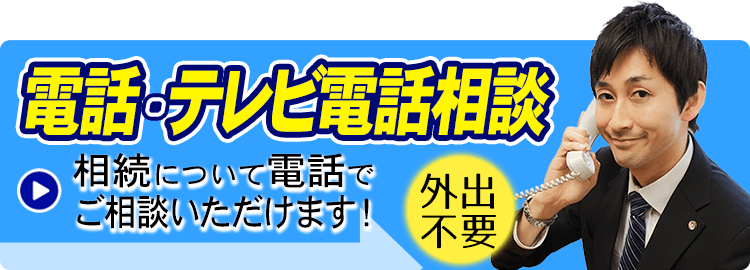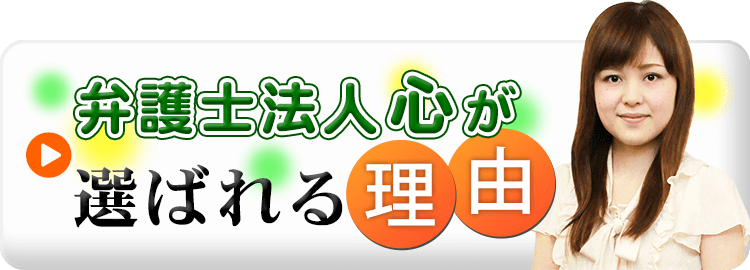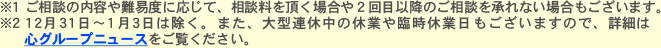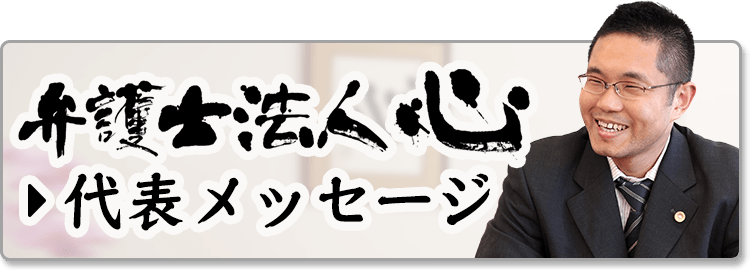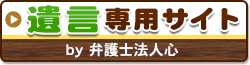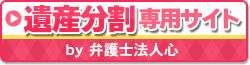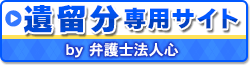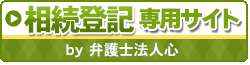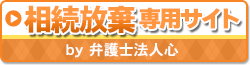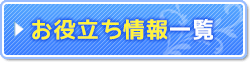兄弟に遺留分は認められるのかについてのQ&A
兄が亡くなり、全財産を姉に相続させる遺言書がありました。弟である私は、姉に遺留分の請求ができますか?
遺留分の請求はできません。
遺留分の請求ができるのは、亡くなった方の配偶者、子(孫)、親(祖父母)だけです。
亡くなった方の兄弟姉妹や、その子である甥姪は、遺留分の請求をすることができません。
なぜ、兄弟姉妹には、遺留分が認められていないのですか?
遺留分という制度は、一定の範囲の相続人に対して、相続の権利をある程度まで保障する制度です。
一定の範囲とは、亡くなった方と近しい存在で、亡くなった方の財産に期待を持つであろう人や、亡くなった方の財産形成の役に立ったであろう人を指します。
この「一定の範囲」をどこで区切るかは、法律を作る国会の判断次第ですが、日本では、配偶者、子(孫)、親(祖父母)までと定めています。
つまり、亡くなった方にとっての配偶者、子(孫)、親(祖父母)は、亡くなった方と比較的近しい存在であることが多いため、亡くなった方の財産に対する期待を保護すべきであると、法は考えているということです。
私は、ずっと兄の生活費を援助してきました。それにもかかわらず、弟である私には遺留分はないのですか?
残念ながら、生前にお兄さんに財産の援助をしていたとしても、遺留分は認められません。
遺留分の制度の趣旨は、亡くなった方と近しい親族の、遺産に対する期待の保護なので、そういった趣旨からすれば、お兄さんを特別に援助していた弟には、遺留分が認められるべきとも思えます。
しかし、どういった援助をすれば、どれくらい保護されるのかという判断は、ケースバイケースであり、個別の判断は困難です。
そこで、法律は、援助の有無などと関係なく、遺留分を認める範囲を一律で定めています。
遺留分の期限についてのQ&A 生前贈与についても遺留分を請求できますか?