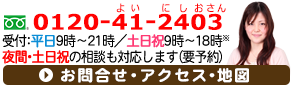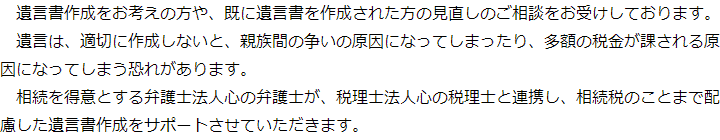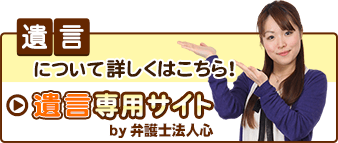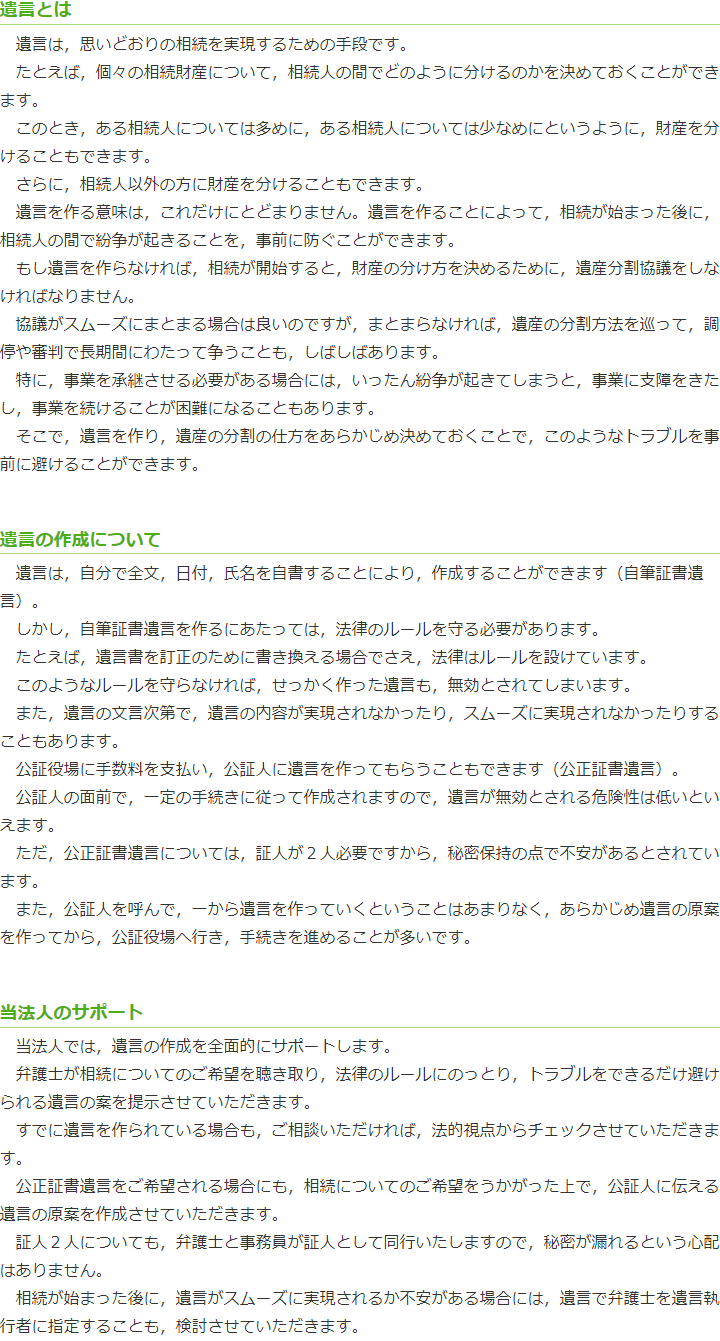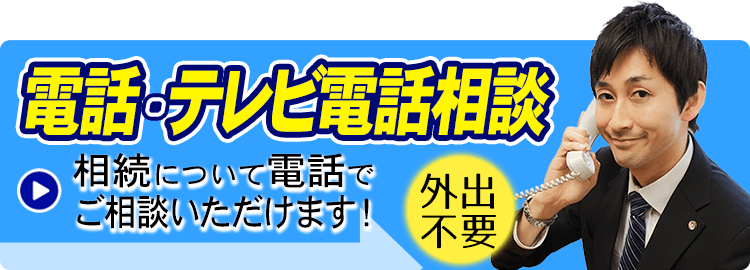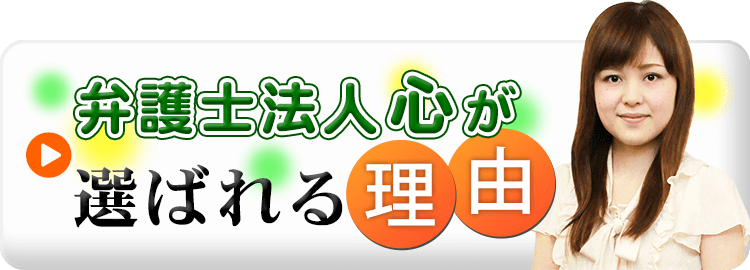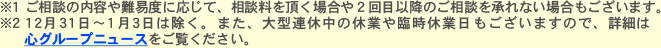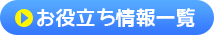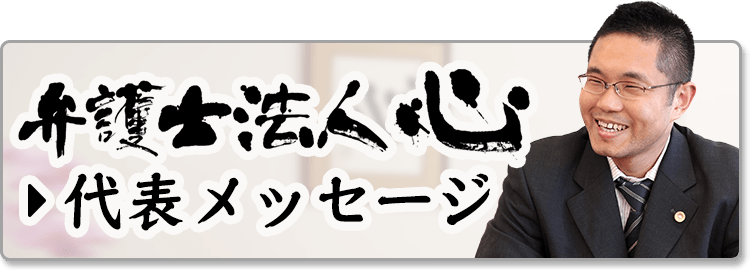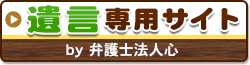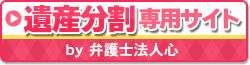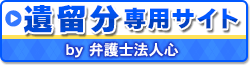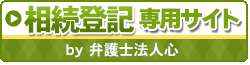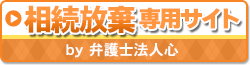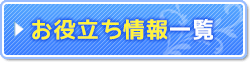遺言
遺言について弁護士に相談したい方へ
1 遺言で失敗すると、取り返しがつかないことも

遺言は一度作成した後も、いつでも作り直すことができます。
そのため、「まずはどんな内容でもいいので、遺言を書いてみることが大切です」といったアドバイスを受けることがあります。
そのアドバイス自体は間違いではありませんが、一度作成した遺言は、その遺言が撤回されるまでは有効な遺言であり続けます。
従って、遺言を作成する際には、たとえ後で本格的に書き直す場合であっても、慎重な対応が求められます。
2 何が目的なのかを明確にすることが大切
特に目的もなく、遺言を作成される方は少ないはずです。
残された家族が遺産の分け方で揉めてしまうことを防ぐという目的があったり、お世話になった恩人にお礼がしたいという目的があったりするなど、様々な目的が考えられますが、作成にあたっては何らかの目的があるはずです。
どんな目的があるのかによって、遺言の内容は大きく変わるため、まずは遺言を作成する目的を決めることが大切です。
3 遺言の相談先は弁護士が適任です
遺言には、将来の紛争を防ぐという大切な役割があります。
どんな遺言があれば紛争を防ぐことができるのか、反対にどういった場合に紛争が起きてしまうのかといった点に精通していなければ、遺言の内容の相談は難しい面があります。
そのため、遺言の相談をする際には、紛争問題を取り扱うことのできる弁護士に相談するのが適切であると考えられます。
4 税金面も考慮する必要があります
遺言の作成においては、税金面の知識が必要になる場合もあります。
遺言で遺産の分け方を指定する場合、誰が何を相続するかによって、相続に関する税金の額が大きく変わることがあるため、遺言の作成にあたっては、税金面についても気を配ることが大切です。
しかし、弁護士は、必ずしも税金に詳しいわけではありません。
そのため、税理士と連携の取れる事務所に相談されることをおすすめします。
遺言執行者は誰にするのが良いか
1 遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言書に表示された被相続人の意思を実現していく権限を与えられた者を指します。
そのため、遺言執行者になれるのは弁護士等の専門家のみであると考えられがちですが、遺言執行者は以下に掲げる事由がない限り誰でもなることができます。
2 欠格事由
以下の事由がある人は遺言執行者になることができません。
- ① 破産者
- ② 未成年者
破産者とは、破産手続きの申立てを行い、その開始決定がなされた後、免責許可決定がでるまでの期間中である方を指します。
3 相続人にする場合
では、遺言執行者を相続人にするのが良い場合とはどのような場合なのでしょうか。
それは、被相続人の財産が少ない場合であったり、どの銀行の口座はどの相続人に渡す等で遺言の内容が単純明快であったりする場合です。
例えば、土地建物はAに相続させ、預貯金口座は全てBに相続させるという内容の遺言書であれば、遺言執行者となったAは、A名義の土地建物の相続登記と、B名義の預貯金の名義変更手続きさえ行えばよいのでその作業は単純です。
しかし、これが例えば、土地建物については、二世帯住宅の一階部分についてはA、二階部分についてはBに相続させ、土地についてはABの共有とする場合や、預貯金口座の内、3分の1は特定の社団に寄付し、3分の2をABで分ける場合等のように、その内容が複雑化する場合には専門家に任せることで相続人の負担を減らせるといえます。
また、以下のように専門家に任せるべき事案もあります。
4 弁護士等の専門家にする場合
遺言執行者を専門家に任せるべき場合は以下のとおりです。
- ① 子供を死後認知する場合
- ② 相続人を遺言排除する場合や排除の取消しを行う場合
①、②については、遺言執行者を選任しなければならない場合として法定されており、その申立ての内容も法的に高度なものであるため専門家に事前に任せる必要があるといえます。